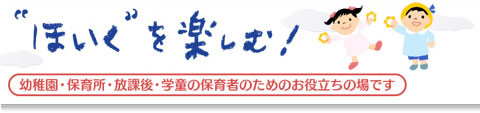 |
 |
||||||

|

|
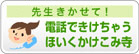
|

|

|
広島大学大学院生物圏科学研究科 谷田 創
はじめに
日本では、古くから幼稚園や小学校において動物飼育が行われていましたが、近年、これらの動物飼育についても動物介在教育の一環として体系化し、具体的な教育目標を設定するとともに、その教育効果を科学的に評価する試みがなされるようになってきました。海外では、動物を飼うだけではなく、子どもたちが積極的に動物と関わりを持つことで、様々な教育効果が期待できると考えられています。
その背景には、都市化が進み、子どもたちの身の回りから自然が失われつつある現状において、環境教育の一環として動物介在教育に期待する声があります。また、近年の犯罪の低年齢化と凶悪化に対しての抑止力として、動物飼育を通した命の教育に注目が集まっています。さらに、子どもたちに対するアニマル・セラピーの効果が社会的に認知されるようになってきたこともあるのではないでしょうか。
しかし、動物介在教育に対して過度の期待を抱くことは禁物です。動物は「魔法の杖」ではありません。私たちの身の回りには、動物が起こした奇跡や、動物と人との心温まる逸話などが多くあります。私自身も動物を飼っていますので、ペットたちの不思議な力を他人に吹聴したくなることもあります。しかし、科学的な検証なしに、個人の経験や思い込みだけが一人歩きしてしまうことは、人間にとっても動物にとっても不幸なことだと思います。そこで本講演では、疑似科学とのそしりを受けないように、科学的な視点から動物介在教育について解説するつもりです。
動物介在教育は「地球を守れ」とは教えない?
最近のテレビや新聞では、地球温暖化と環境保護に関連した番組や記事が連日にぎわっています。少し前までは環境問題を口にする人間は変わり者というレッテルが貼られていたのに、今では環境問題に関心のない人間が白い目で見られるようになりました。
私たちの身の回りでも、夏の最高気温が年々更新され、雪を見ない冬の日が増えていますし、突然の豪雨や竜巻などによる災害などが頻発し、自然の猛威に対する人間の無力さを感じさせられる出来事ばかりに遭遇します。近年の温暖化は地球環境の変動の範囲内であり、人類の責任ではないとする意見もありますが、これまでの私たちの営みが環境破壊を急速に進行させているとの指摘が大勢を占めています。今のうちに手を打たないと地球の未来はないという声や、もう手遅れだとする悲痛な叫びもあります。これらの様々な思いが、「地球を守りましょう=地球にやさしくしましょう=エコロジー」というフレーズとなって世の中に氾濫しているのかもしれませんが、私は、「地球を守る」「地球にやさしく」という表現が本当に適切なのか疑問を感じています。
生物が地球上に姿を現したのは36億年ほど前であると言われていますが、その長い歴史の中で、人類の誕生はつい数百万年前の最近の出来事です。地球にとっては新生児であるこの人類が、産みの母である地球を守ることは本当に可能なのでしょうか。
例えば、地球を金魚鉢に見立てて、人類を金魚に置き換えて考えてみましょう。金魚鉢が割れて水がなくなっても、金魚が増えすぎて水が腐敗したり、水草が枯れて酸素不足になったりしても金魚は死にます。金魚には自分で水を換えたり水草を植えたりする力はありません。しかし人類は、「自分たちは金魚ほどあさはかでも無力でもなく、科学の力を使えばひび割れた金魚鉢を補修したり、水を入れ替えたり、水草を植えたりすることが可能で、金魚鉢を復活させることができる」と信じているようです。
しかし、金魚に、金魚鉢の未来を変えることができるでしょうか。私たち人類が今後も生存して行くためには、すべての生物と協調して生きようとする姿勢をもつことが不可欠です。「地球を守ろう」と不可能なことを呪文のように連呼するのではなく、他の生き物の命に対する私達の思いやりと責任を具体的に自覚することが必要だと思うのです。
動物介在教育では、動物とのふれあいを通して、命あるもの同士の連帯感を子どもたちに体験してもらいたいと思っています。私が目指す動物介在教育の目標とは、「生き物との関わりを通して、他者の存在を認め、自分が生きるためには他者の力が必要であることに気づき、他者と共存しながら生きてゆける子どもを育てる」ことにあります(他者には人間と人間以外の生き物が含まれます)。動物介在教育を通して人間性の豊かな子どもを育てるということは、「その子どもの成長あるいは向上、幸福にだけに目を向けるのではなく、他者の幸せの上に自分の幸せがあることを自覚できる人間を育てる」ことであると思います。
動物を介在して心の窓を開く
ホース・セラピー(乗馬療法)やイルカ・セラピー(イルカ療法)などのアニマル・セラピーについてはご存知の方もおられると思います。これらのセラピーでは、発達障害を持った子どもの治療や、不登校などの心の問題を抱えた子どもの心のケア、身体的機能障害を持った人などに対するリハビリテーション医療などに、馬やイルカなどの動物が用いられ、その効果が認められるようになってきました。子どもたちや患者は、動物に触れることによって、言葉を介しない手段で他者(動物)との交流を経験します。
日本では、アニマル・セラピーと呼ばれていますが、アニマル・アシステッド・セラピー(以下動物介在療法:Animal Assisted Therapy, AAT)とアニマル・アシステッド・アクティビティー(以下動物介在活動:Animal Assisted Activity, AAA)とに区別すべきだという意見もあります。
動物介在療法は、医療に関わる資格を持った医師や看護士、ソーシャルワーカー、作業・心理・言語療法士などが、動物を連れたボランティアと協力して、患者の心身の機能を回復するために治療目標を設定し、計画的に実施するものです。実施に際しては、患者に対する経過観察の専門的な記録と、治療効果の評価が求められます。また、活動に参加する動物の適性も厳密に評価されます。
動物介在活動は、ボランティアが中心となって計画し、自由意志で参加した者が様々な施設や屋外で動物とのふれあいを楽しむ活動です。高齢者施設への動物の訪問活動などがあります。動物介在活動が患者を対象としている場合は、治療的な効果が見られることがあっても、専門家の客観的な評価なしにこれをセラピーと呼ぶことはできません。
動物介在療法も動物介在活動も、対象者である子どもや患者個人の健康と福祉の向上を目指すものですが、それとともに、他者との心の交流回路(心の窓)を開放することで、他者を認識し、他者との関係を向上させる働きがあります。他者には、動物介在療法や動物介在活動に携わる人や参加者、その橋渡しをする動物たちに加えて、心の中に存在するもう一人の自分も含まれるのかもしれません。
動物介在教育は他者を通して自己を見つめる教育である
動物介在教育、アニマル・アシステッド・エデュケーション(Animal Assisted Education :AAE)は、以前はアニマル・セラピーの一つとして認識されていたこともありました。しかし、動物介在療法や動物介在活動とは担っている役割が異なるので、療法や活動とは区別して動物介在教育を捉えるようになってきました。
動物介在教育は、教育の場で動物を介在させた(動物の助けを借りた)教育全般を指すものですが、広く認められた明確な定義は存在しません。しかし、先にも述べたように、私が目指す「動物介在教育」の目標とは、「生き物との関わりを通して、他者(人類だけではなくすべての生物を含む)の存在を認め、自分が生きるためには他者の力が必要であることに気づき、他者と共存しながら生きてゆける子どもを育てる」ことにあります。
教育効果としては、IQや知識を高めるといった個々の子どもの能力の開発よりも、結果的に、教育の成果が人間社会と人間以外の生物に対してどのような貢献ができるのかが重要であると考えています。言葉を持たない生き物との交流を通して、生き物の気持ちや痛みを察する心と習慣を身につけ、身近な人から、社会、世界の人々、すべての生きとし生ける物にまで目を向けてゆくことが、人類とすべての生物の生存にとって必要なことであると思います。
広がりを見せる動物介在教育
日本で動物介在教育として思い浮かぶのは、幼稚園や小学校などの教育施設でウサギやニワトリなどの動物を飼育し、子どもたちに世話をさせる活動です。すでに明治時代には、幼稚園において小鳥、金魚、カイコ、ウサギ、ニワトリ、ハト、オタマジャクシなどが飼育されていたようです。現在の幼稚園や小学校においてもこの動物飼育の歴史が連綿と受け継がれていますが、教育機関における動物飼育は、「ともすればその責任体制が不明確になる」「休日の飼育管理が行き届かない」「教員の知識不足から動物を適切に飼育できない」「動物が増えすぎる」「教育効果の評価が難しい」「動物が死んだ時の対処に困る」など、今後改善してゆかなければならない問題もあります。
また、クラスの中で飼育されている動物を介した教育とともに、最近では、幼稚園や小学校に犬や猫などの動物を連れて行く訪問型の動物介在教育も実施されています。各地の動物保護センターの職員や動物愛護団体のボランティアが動物を伴って幼稚園や小学校などを訪問し、動物愛護の精神や動物とのつき合い方を教える活動です。訪問活動では、最初に、犬と猫の性質や特徴、ふれあい方の基本を説明します。ペットブームの一方で、子どもたちが犬に咬まれる事件が多く発生していますが、その原因は、犬の躾の不備による事故とともに、子どもたちが犬への近づき方や触り方を知らないことによる事故もあり、子どものうちに動物との正しい付き合い方を学ばせることが必要とされています。
また、米国では、主に学齢期の子どもたちの読書力を高めるために、犬を介在させて読書をするR.E.A.D.プログラムが行われています。図書館などの公共施設や学校にボランティアが連れて来た犬に子どもたちが朗読するという方法を通して、子どもたちの読書能力とコミュニケーション能力を改善することを目指しています。
一方、日本では食と農を一体化して教える「食農教育」が近年注目されています。食育基本法(2005年)に基づいて作成された食育推進基本計画(2006年 食育推進会議決定 )には「農作業等の体験の機会を提供する教育ファームを推進する」と明記されています。私も大学の附属農場において、「食と命の学びを支援すること」を目的として、子どもたちに酪農の現場を体験させる活動をしています。これも動物介在教育の一形態であると考えています。
まとめ
国内外における動物介在教育の取り組み例、科学的見地に基づいた教育効果などについて紹介しながら、皆さんと一緒に動物介在教育の意味を考えてみたいと思います。
ページトップへ↑
http://www.hoiku-support.jp/cmt/mt-tb.cgi/111
※ブログ作成者から承認されるまでトラックバックは反映されません
コメントする