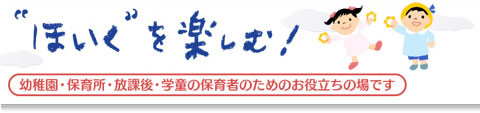 |
 |
||||||

|

|
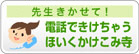
|

|

|
- 明らかに身体的な障害があるのに、保護者からの情報がいただけません。どのようなかかわり方をしていったらいいのでしょう。
- 少しでも子どもにとって有効な対応をしたいと、保護者との連携を願っていらっしゃるのですね。まずは、信頼関係を深めることからはじめましょう。
身体的に障害のあるお子さんの保護者は、口には出さなくても、わが子の障害を充分に認めていらっしゃいます。耳・口・足・手などの奇形や障害を見過ごすことなどはできません......。でも、事実を口にすることは、とてもつらいことなのです。わが子の障害を、第三者的に認めることになるからです......。
うれしいはずの誕生のときから、手放しで喜べなかった複雑な思い......。察するにあまりあることでしょう。とても悲しく、苦しい胸の内を、深く思いやってあげましょう。産声に感動した瞬間、だれもが信じたい「五体満足」。その後の大きな驚き、とまどい、悲しみ......。今に至っても、ずっしりと胸の奥に閉じ込めていらっしゃるのでしょう。そんな思いは、私たちがどんなにくみ取ろうと努めても、十二分にわかり切れるものではありません。保護者は、だれにもぶつけようのない葛藤の日々を過ごしていらっしゃるのでしょう。
だから、家族以外の人に障害の内容について冷静に話すことは、むずかしいのです。
「子どもの障害について、だれにも話したくない」「だれからもさわられたくない」。そんな心の叫びにやさしく耳を傾け、深い心で受け止めてあげましょう。
保護者は、保育者に心を閉ざしていらっしゃるのではありません。
「わが子を守らなければ......」という思いから、子どもを取り巻く環境(ことに人的環境)、すべてに心を閉ざす状況。あるいは、子どもの状態を「認めたくない」という気持ちから、「現実を見たくない」「感じたくない」という逃避の状況など......様々な状況が考えられます。
しかし、日々成長していく子どもは、障害のありようが変化していきます。
ときに、少しずつ改善され、克服され、保護者が励まされ、勇気づけられることもあるでしょう。ときに、さらに特徴的な変化が出て、さらに心を痛められることもあるでしょう。様々な場面で、保護者の立場になって考えてみましょう。
私は、園の生活に支障がない限り、保護者からの説明の範囲で対処したいと思っています。例えば、「指が3本しかありませんが......」などと、身体的特徴についてだけ質問をしても、保護者には答えようもなく、困惑されるだけです。
そんなときは、3本の指で生活ができるようにするための援助を様々に試みてみます。物が持てるようになるために、物がつかめるようになるために、ボタンかけや、パンツやズボンのあげさげに困らないように。どんなハサミが使えるのか、どんな大きさのパスが描きやすいのか、どんな楽器から取り組んだら楽しめるのか。生活やあそびの場面での不都合を、子ども側の視点に立って、子ども自身が克服していけるような援助を試みます。
保護者が子どもの障害について、率直にお話くださるのは、子どものチャレンジする姿に感動されたとき。それは、喜びと、安心と、励ましを子どもが伝えてくれるからです。保育者の温かなメッセージ、深い思いやり、努力もそんな状況の中から届くのでしょう。そこに至るまでに、半年や一年、ときには二年あまりの歳月が必要なこともあります。
保育者としてできることを、園医さん、保健婦さん、児童相談所などの機関をフルに活用して教えていただきましょう。
うれしいはずの誕生のときから、手放しで喜べなかった複雑な思い......。察するにあまりあることでしょう。とても悲しく、苦しい胸の内を、深く思いやってあげましょう。産声に感動した瞬間、だれもが信じたい「五体満足」。その後の大きな驚き、とまどい、悲しみ......。今に至っても、ずっしりと胸の奥に閉じ込めていらっしゃるのでしょう。そんな思いは、私たちがどんなにくみ取ろうと努めても、十二分にわかり切れるものではありません。保護者は、だれにもぶつけようのない葛藤の日々を過ごしていらっしゃるのでしょう。
だから、家族以外の人に障害の内容について冷静に話すことは、むずかしいのです。
「子どもの障害について、だれにも話したくない」「だれからもさわられたくない」。そんな心の叫びにやさしく耳を傾け、深い心で受け止めてあげましょう。
保護者は、保育者に心を閉ざしていらっしゃるのではありません。
「わが子を守らなければ......」という思いから、子どもを取り巻く環境(ことに人的環境)、すべてに心を閉ざす状況。あるいは、子どもの状態を「認めたくない」という気持ちから、「現実を見たくない」「感じたくない」という逃避の状況など......様々な状況が考えられます。
しかし、日々成長していく子どもは、障害のありようが変化していきます。
ときに、少しずつ改善され、克服され、保護者が励まされ、勇気づけられることもあるでしょう。ときに、さらに特徴的な変化が出て、さらに心を痛められることもあるでしょう。様々な場面で、保護者の立場になって考えてみましょう。
私は、園の生活に支障がない限り、保護者からの説明の範囲で対処したいと思っています。例えば、「指が3本しかありませんが......」などと、身体的特徴についてだけ質問をしても、保護者には答えようもなく、困惑されるだけです。
そんなときは、3本の指で生活ができるようにするための援助を様々に試みてみます。物が持てるようになるために、物がつかめるようになるために、ボタンかけや、パンツやズボンのあげさげに困らないように。どんなハサミが使えるのか、どんな大きさのパスが描きやすいのか、どんな楽器から取り組んだら楽しめるのか。生活やあそびの場面での不都合を、子ども側の視点に立って、子ども自身が克服していけるような援助を試みます。
保護者が子どもの障害について、率直にお話くださるのは、子どものチャレンジする姿に感動されたとき。それは、喜びと、安心と、励ましを子どもが伝えてくれるからです。保育者の温かなメッセージ、深い思いやり、努力もそんな状況の中から届くのでしょう。そこに至るまでに、半年や一年、ときには二年あまりの歳月が必要なこともあります。
保育者としてできることを、園医さん、保健婦さん、児童相談所などの機関をフルに活用して教えていただきましょう。
ページトップへ↑
この記事へのトラックバック
この記事のトラックバック Ping-URL
http://www.hoiku-support.jp/cmt/mt-tb.cgi/100
※ブログ作成者から承認されるまでトラックバックは反映されません
http://www.hoiku-support.jp/cmt/mt-tb.cgi/100
※ブログ作成者から承認されるまでトラックバックは反映されません
このホームページの製作に当たっては、「競輪公益資金」の補助を受けました。 Copylight 2008 kinoshita-zaidan. Allreserved
コメントする